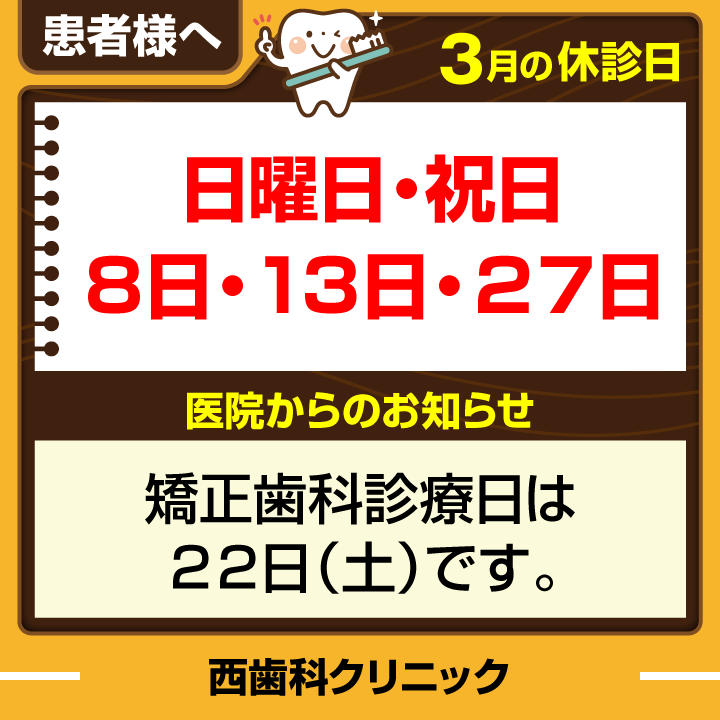
カテゴリー: 未分類
10代に異変多数!顔のゆがみは口の中に原因が⁉

こんにちは。院長の西です。
2月28日は日本で初めてビスケットが作られたことから
「ビスケットの日」とされています。
ビスケットの歴史は古く、古代ヨーロッパ人が
航海に携えた硬い保存食が
起源と言われています。
現代では広く親しまれているビスケットですが、
最近、若い世代ではこのような硬い食べものよりも、
やわらかい食べもののほうが
好まれる傾向にあります。
そして、この傾向が
身体の発達に深く関わる問題として
注目されています。
◆高齢者よりも深刻!10代の「食べる力」
近年、若い世代を中心に
「硬い食べもの離れ」が進んでいます。
これは、10代のお口の機能の発達に
深刻な影響が及んでいることを
暗に示しています。
日本歯科医師会の調査によると、
10代の2人に1人が
食事中にあごの疲れを感じており、
その割合は70代の2.7倍に及ぶことがわかりました。
同調査ではほかにも、若い人の間で
「滑舌が悪い」「食べこぼしが多い」
といった症状も多数報告されており、
10代の「食べる力」の低下が大きな問題となっています。
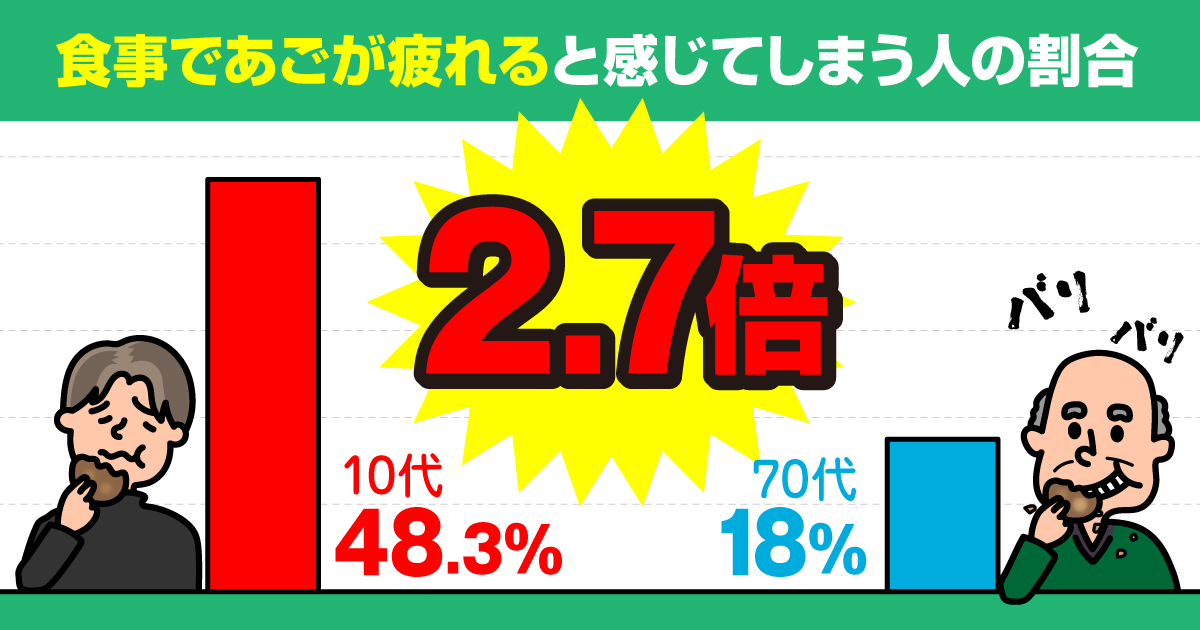
これらの症状は「口腔機能発達不全症」として、
近年歯科医療の現場でも重要視されています。
◆顔つきや発音にも影響?
「口腔機能発達不全症」とは
口腔機能発達不全症は、
2018年に新しく保険適用となった病名で、
18歳未満の子どもに見られる、
口腔機能の発達の遅れを示しています。
「食べる」「話す」「呼吸する」
といった日常の動作は、噛む筋肉や
あごの骨の発達にも深く関わっています。
これらの機能が
十分に発達しないまま放置すると、
筋肉やあごの正常な発育が妨げられ、
次のような問題を招いてしまうおそれがあります。
・歯並びやかみ合わせが悪くなる
・顔の形にゆがみが生じる
・発音が不明瞭(滑舌が悪い)
・鼻腔や気道が狭くなり、呼吸がしづらくなる
・噛む力の低下により、成長期に必要な栄養が不足する

◆早期の対応が重要!今すぐチェック!
口腔機能発達不全症は
早い段階での気づきと適切なケアにより、
多くの場合で改善が期待できる病気です。
一方で、「食べこぼし」や
「ゆっくり食べる習慣」など、
その兆候は子育ての日常でよく見られるものも多く、
そのまま見過ごされてしまうことも
少なくありません。

口腔機能発達不全症は、
「食べる」「話す」「その他(体格など)」の
各項目のチェックリストにより診断されます。
以下に基準の一部を記載しますので、
これらをはじめ、お口の機能に不安がある場合は、
お早めに当院までご相談ください。
□咀しゃく時間が長すぎる(または短すぎる)
□食事の量や回数が多すぎる
(または少なすぎる、ムラがある)
□「カ・サ・タ・ナ・ラ」行がうまく発音できない
□いつも口を開けて息をしている
□睡眠時のいびきがある
西歯科クリニック
〒619-0218
京都府木津川市城山台1-14-1
TEL:0774-73-6767
URL:https://nishi-dc.net/
Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm
放置NG!頬の内側を噛む原因と対処法

あけましておめでとうございます。
院長の西です。
毎年1月7日は七草がゆを食べて邪気を払い、
1年の無病息災を願う「七草の日」です。
七草がゆをはじめ、
日々の食事を楽しみつつ
十分な栄養を取り込むためにも、
お口の状態は常に良好に保ちたいですね。
しかし、ふとしたときに頬の内側を噛んでしまうと、
食事の楽しみにも影響を及ぼします。
中でも、頬を噛む頻度が高い方は
さらなるトラブルに繋がるおそれがあるため
要注意です。
そこで、今回は頬を噛んでしまう原因と
対処法をご紹介します。
◆原因1:歯ぎしり・食いしばり
頬を噛む原因として、
歯ぎしりや食いしばりが
挙げられます。
歯は本来、噛んだときに
頬を巻き込まない形状をしています。
しかし、夜間の歯ぎしりや
日中の食いしばりによって
徐々に歯は削られていきます。
これにより歯の形や
かみ合わせが変化することで、
頬を噛みやすくなってしまうのです。

このようなケースには、
専用のマウスピース(ナイトガード)の
使用が有効です。
主に就寝時にナイトガードを着用して
歯を保護することで、
頬を巻き込んで噛むリスクを
減らすことができます。
◆原因2:親知らず
親知らずも頬を噛みやすくなる
原因のひとつです。
お口の中では奥歯に行くほど、
歯と頬の粘膜の距離が近づきます。
その中でも、親知らずは
お口の最も奥に生えるため、
頬の粘膜と接触しやすくなります。
とくに、親知らずは
真っすぐに生えないことも多く、
横向きや斜め向きに生えてくると
接触するリスクが高まります。

このように、親知らずが原因で
頬を噛みやすくなった場合は、
主に抜歯などの方法で改善を目指します。
◆原因3:かぶせもの・入れ歯のトラブル
歯科での治療直後に頬を噛みやすくなった場合、
新たに入れたかぶせものが
お口に合っていないことが考えられます。
また、入れ歯をお使いの方は、
長年の使用により、
入れ歯の歯がすり減ることで、
頬の内側を噛みやすくなります。
これらが原因と思われる場合は、
歯科でかぶせものの調整や、
入れ歯の修理、作り直しなどを行い、
改善に向けた対処をしていきます。
◆症状に心当たりがあれば早めの相談を!
食事中など、
まれに頬の内側を噛む程度であれば、
さほど気にはならないかもしれません。
しかし、これが何度も繰り返されると、
食事の楽しみを損なうだけでなく、
口内炎などのトラブルを
引き起こすおそれもあります。
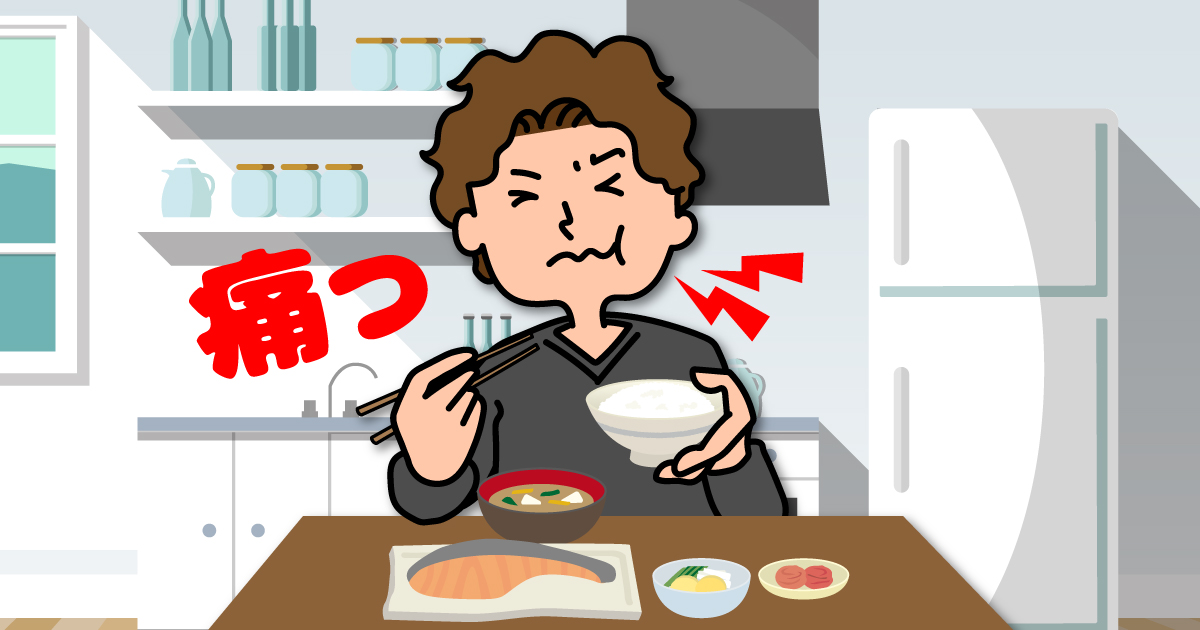
お口の快適な状態を保つためにも、
たびたび頬を噛んでしまうことに心当たりがあれば、
まずはお気兼ねなく当院へご相談ください。
西歯科クリニック
〒619-0218
京都府木津川市城山台1-14-1
TEL:0774-73-6767
URL:https://nishi-dc.net/
Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm
口臭の原因は舌にあり!?正しい舌ケアでいざ改善!

こんにちは。院長の西です。
12月13日は「煤払い(すすはらい)の日」です。
古来より、この日に家中を清めて
新年を迎える準備をする習慣があり、
これが現在の「大掃除」の
ルーツになったといわれています。
今年のうちに身の回りをきれいにして、
気持ちも新たに新年を迎えたいですね。
さて、大掃除と同じくして、
お口の中も汚れを落として清潔にし、
日々快適に過ごしたいものです。
実は、お口の中では歯だけでなく、
舌の汚れもさまざまなトラブルの
原因となり得るため、注意が必要です。
◆舌の白い汚れの正体は?
鏡の前で舌を出したとき、
まるで薄雪が積もったように
表面が白くなっていることはありませんか?
この白い付着物は
「舌苔(ぜったい)」と呼ばれるもので、
食べかすやだ液の成分、口内ではがれ落ちた粘膜、
細菌などが原因で発生する舌の汚れです。
実は、この舌苔が
口臭の主な発生源となっているのです。
これは、舌苔に含まれる細菌が
悪臭のもととなる物質を作り出すためで、
舌苔が厚くなると
口臭も強くなってしまいます。

さらに、舌苔が厚くなると味覚を鈍らせ、
味を感じにくくさせるおそれもあるため、
気になる方はしっかり対処しましょう。
◆舌苔が増えやすくなる環境に要注意!
先に述べたように、舌苔は厚くなるほど、
口臭などの悪化リスクが高まります。
とくに、以下の環境下では
舌苔が厚くなりやすいため、注意が必要です。
・不衛生な状態
歯みがきが不十分な場合、
口内が不衛生になり、菌やはがれた粘膜が
舌に付着しやすくなります。
・乾燥した状態
口内でだ液の分泌量が減少し、
だ液が持つ自浄作用や
殺菌作用が十分に機能せず、
舌苔が厚くなる原因となります。
口呼吸やストレスなど、
無意識な習慣も乾燥の原因となるため、
日頃から意識的に対策することが望ましいです。
◆今日から実践! 正しい舌ケア法
舌苔を予防・除去するためには
「舌ケア」が効果的です。
以下のポイントをおさえて、
毎日の習慣にしましょう。
・専用の舌ブラシを使用する
表面を傷つけないように、
やわらかい素材の舌ブラシの使用がおすすめです。
・奥から前方へ、一方向に動かす
舌の奥から前方へ、
一方向に優しく舌ブラシを動かします。
少しずつ横に移動しながら、
3回程度で汚れをかき出しましょう。
・1日1回、起床時に行う
寝ている間に細菌が増殖するため、
朝一番のケアがおすすめです。
・やりすぎに注意
舌はとてもデリケートな部位です。
一度にすべての舌苔を取り除こうとはせず、
数日かけて少しずつケアしていきましょう。

◆舌ケアの疑問は歯科医院で解決!
舌のお手入れは
ご家庭でも簡単に行えますが、
誤ったケアは思わぬトラブルを
引き起こすおそれがあります。
力を入れすぎたり、
過度にケアを行ったりすると
舌を傷つけてしまい、
かえって口臭が強くなることもあるため
注意が必要です。

当院では、一人ひとりのお口の状態に合わせて、
正しい舌ケアの方法をアドバイスしています。
舌の状態にお悩みがある方は、
お気軽にご相談ください。
西歯科クリニック
〒619-0218
京都府木津川市城山台1-14-1
TEL:0774-73-6767
URL:https://nishi-dc.net/
Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm
治療後も油断禁物!つめもの・かぶせものの寿命

こんにちは。院長の西です。
今年の11月7日は暦の上で
冬の始まりを告げる立冬です。
来る寒さに備えて、冬支度を始める方も
多いのではないでしょうか。
暖房器具や冬物の衣類は
早めに手入れを済ませて準備しておきたいですね。
さて、お口においても日ごろの手入れが欠かせませんが、
実は、治療した後のつめものやかぶせものも、
その後のセルフケアやチェックが大切です。
そこで今回は、
治療後のつめものやかぶせものの注意点について
お話ししていきます。
◆一生モノじゃない!?
つめものやかぶせものの寿命
歯科で治療を受けて、
つめものやかぶせものが入ると
「これで一安心」
と思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、この時点では歯の不安を
完全に払拭することはできません。
これらの修復物には寿命があり、
ある調査では金属のつめもので5.4年、
かぶせもので7.1年、ブリッジで8年が
それぞれの平均使用年数といわれています。
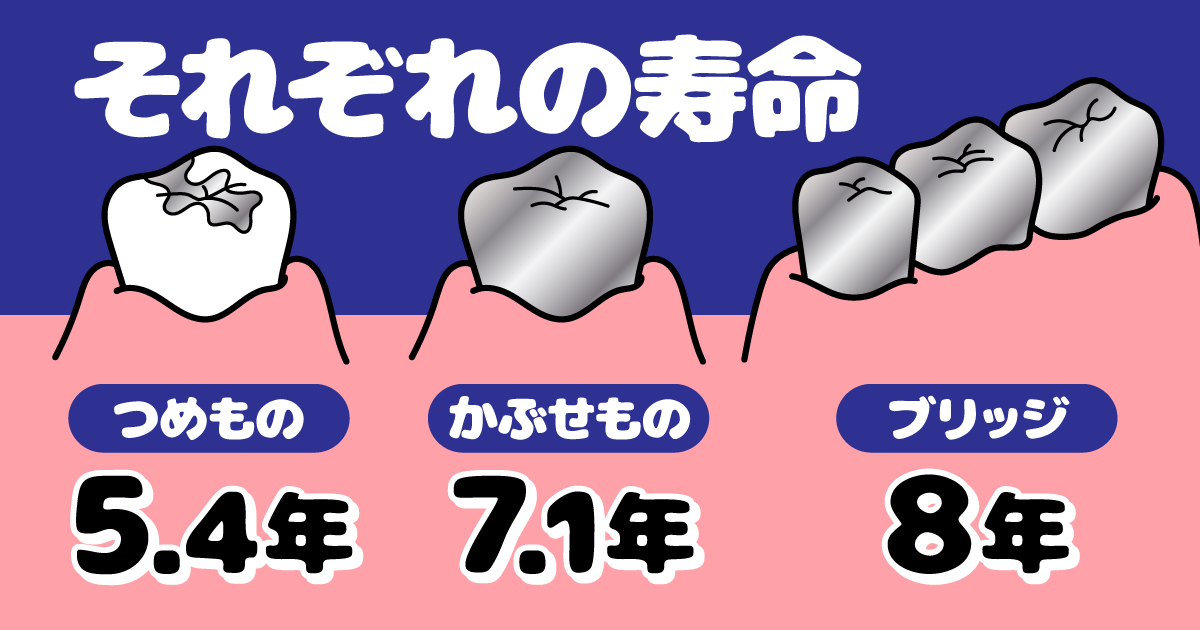
では、なぜつめものやかぶせものは
”一生モノ”ではないのでしょうか。
それは、治療後もお口の中は
環境や状態が常に変化し、
過酷な環境にさらされているからです。
このような環境下において、
治療した部位が同じ状態を長く保ち続けるのは
非常に困難なのです。
◆つめもの・かぶせものの寿命を縮める
危険な因子
つめものやかぶせものの寿命は、お口の中の
さまざまな要因によって左右されます。
たとえば、無意識での歯ぎしりや
食いしばりのくせがある人は、
つめものやかぶせものに非常に強い力が加わり、
やがて割れたり欠けたりするおそれがあります。
また、かみ合わせの変化も
つめものやかぶせものが取れたり
外れたりする要因となり得ます。
これは、治療時点では歯にフィットしていても、
年月とともにかみ合わせのバランスが変わることで
余計な負担がかかるためです。
このように、同じような状況下で入れた
つめもの・かぶせものでも、
個々のお口の状態や習慣などによって、
その寿命が大きく変わってくるのです。
◆見逃されがちな「二次むし歯」に要注意!
つめものやかぶせものの寿命に
影響を与える要因で、もうひとつ忘れてはいけないのが
「二次むし歯」です。
これは一度治療した部位に再度発生するむし歯で、
つめものやかぶせものの装着後であっても、
やがて劣化により生まれたすき間に菌が入り込み、
再び歯を溶かしていきます。
二次むし歯は
自覚症状がないまま進行することが多く、
レントゲンをとって初めてその存在に
気づくことも少なくありません。
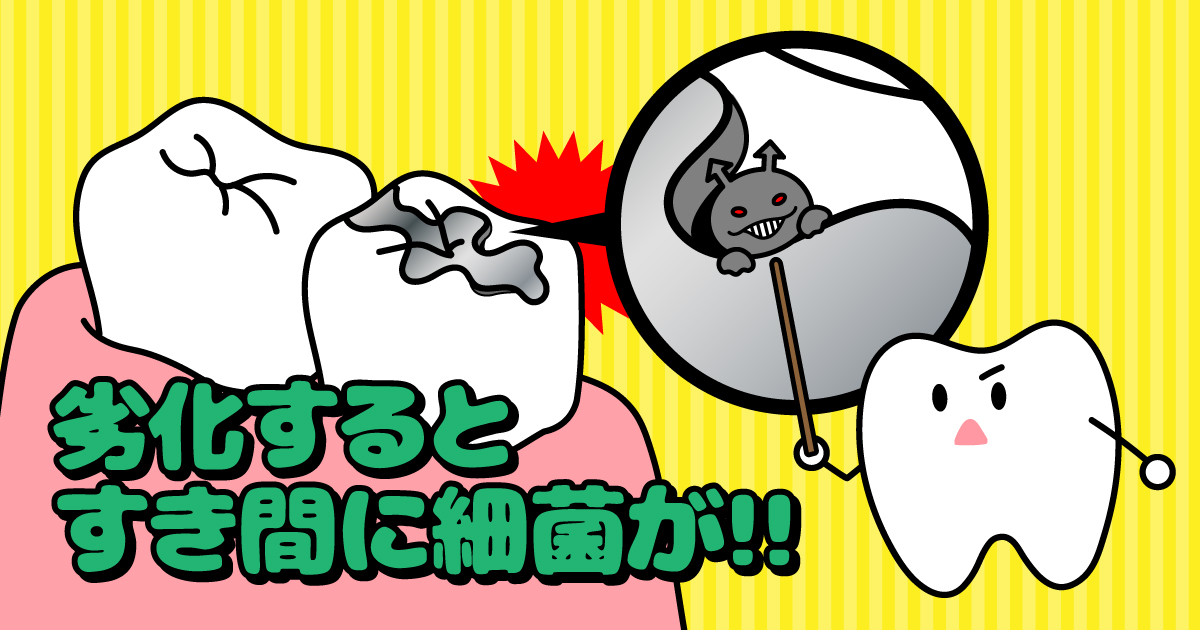
そして、二次むし歯が進行すると、
つめものやかぶせものの適合性が悪くなり、
やがて外れてしまうおそれがあるのです。
そのため、定期的なチェックによる
早期発見が重要となります。
◆長持ちの秘訣はプロのチェック
つめものやかぶせものを長持ちさせるためには
毎日のセルフケアにくわえ、
定期的な歯科受診が欠かせません。

繰り返す治療に悩まされないためにも、
治療後も定期的な受診を継続して、
お口のトラブルを未然に防ぎましょう!
西歯科クリニック
〒619-0218
京都府木津川市城山台1-14-1
TEL:0774-73-6767
URL:https://nishi-dc.net/
Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm
母子ともにリスクが! 妊娠中の口腔ケアの重要性
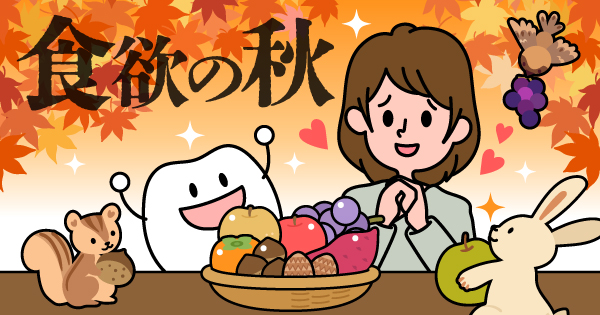
こんにちは。院長の西です。
秋といえば「食欲の秋」。
旬の食材を味わうのが楽しみになる季節です。
旬の食材はおいしいだけでなく
栄養価も高いため、
積極的に食事に取り入れたいですね。
そんな食事が楽しみな季節だからこそ、
お口のケアも欠かせません。
中でも妊娠中の方は
お口のトラブルが起こりやすく、
母子の健康にも悪影響を与えうるため、
特に注意が必要です。
そこで今回は、
妊娠中の口腔ケアの重要性について
お話ししていきます。
◆痛みや不快感も!?
妊娠中に起こりやすいお口のトラブル
かつては
「一子を得ると一歯を失う」
といわれたほど、
妊娠中は口内にさまざまな問題が
発生しやすくなります。
「気分が悪くて、歯が磨けない」
「だ液がネバついて気持ち悪い」
などがその代表例です。

また、妊娠前にはなかった
以下のようなトラブルに悩まされる方も
少なくありません。
・歯や歯ぐきに痛みがある
・歯ぐきに腫れや出血がある
・冷たいものや熱いものがしみる
・口臭が強くなる
◆なぜ妊娠中にお口のトラブルが起きるのか?
その要因のひとつが、妊娠中における
女性ホルモンの分泌量の増加です。
これにより、女性の体には
さまざまな変化が生じます。
これはお口の中も例外ではなく、
サラサラだっただ液が粘り気を増し、
つわりによって
歯みがきが困難になるなどして、
普段よりもお口の中を
清潔に保つ力が弱まります
また、歯周病菌の中には
女性ホルモンによって
活発になる菌が存在することも、
妊娠中に歯ぐきの腫れや
出血が多くなる一因です。
さらに、妊娠後期に入り
お腹が大きくなると、
一度に食べられる食事の量が限られるため、
結果的に食事の回数が増えていきます。
それに応じたケアが不足してしまうことも、
お口のトラブルが増える要因となります。
◆赤ちゃんにも悪影響が!?
妊娠中の歯周病に要注意
妊娠中のお口のトラブルは
お母さんだけの問題ではなく、
赤ちゃんにまで影響する恐れがあります。
その一例が、早産や低体重児出産です。
近年の研究により、妊娠中の歯周病は
早産や低体重児出産のリスクを約2倍~4倍も
高めることがわかっています。
これは、歯周病の原因菌や歯ぐきの炎症が、
子宮の収縮に影響を与えるためと
考えられています。

このことから、
妊娠中はお母さん自身だけではなく
お腹の赤ちゃんの健康を守るためにも、
お口のケアは欠かせません。
◆安定期に入ったら歯科受診を!
妊娠中のお口の健康は、
お母さんと赤ちゃん、双方に大切です。
妊娠安定期(妊娠16週~27週)に入ったら、
ぜひ歯科医院で検査とクリーニングを受けましょう。
また、安定期であれば
必要な歯科治療を受けることも可能です。

定期的なケアでお口の健康を保ち、
安心して出産を迎えられるよう、
私たちも全力でサポートいたします。
妊娠中のお口のケアで気になることがあれば、
お気兼ねなく当院へご相談ください。
西歯科クリニック
〒619-0218
京都府木津川市城山台1-14-1
TEL:0774-73-6767
URL:https://nishi-dc.net/
Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm
お口の衰えは要介護の入り口?「オーラルフレイル」とは
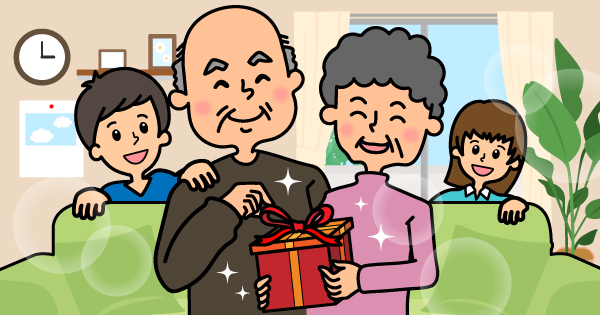
こんにちは。院長の西です。
今年は9月16日が敬老の日ですね。
お年寄りを敬い、
長寿を願う日ということで、
ご高齢のご家族へお祝いをする方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
年を重ねても若々しく
元気に過ごしたいものですが、
実は、加齢による衰えと
お口の状態には深い関わりがあるのです。
そこで今回は、
心身の衰えにつながりうるお口の機能低下、
オーラルフレイルについてお話ししていきます。
◆そのお口の変化
実はオーラルフレイルかも?
食事をしていて、以前よりも
「むせやすくなった」
「食べこぼしが増えた」
と感じたことはないでしょうか。
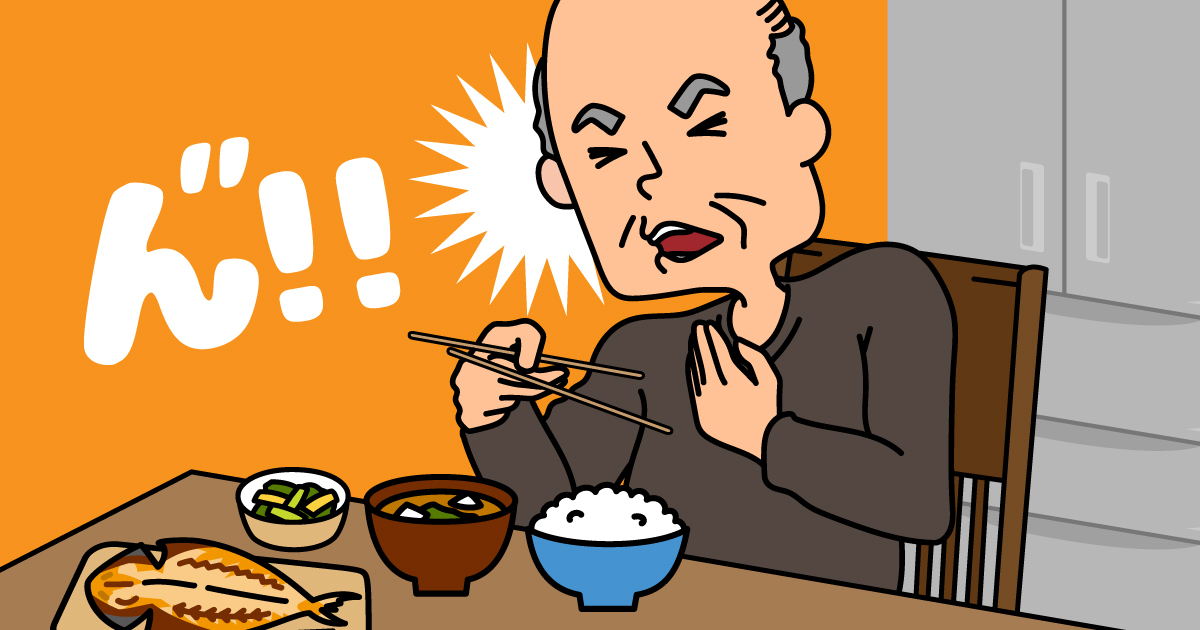
オーラルフレイルとは、
このような日常で感じる
”お口のささいな衰え”のことで、
「健康な状態」と
「お口の機能が低下した状態」の
ちょうど中間に当たります。
この段階で適切な対応を行えば、
元の健康な状態に戻れるのが
オーラルフレイルの大きな特徴です。
一方で、日常生活において、
このようなささいな衰えは
「年をとれば仕方のないこと」
と軽視しがちで、
そのまま放置してしまう方も
少なくありません。
◆放置厳禁!
オーラルフレイルが要介護の原因に!?
オーラルフレイルを放置すると、
その先にはさまざまなリスクが
待ち受けています。
たとえば、「噛みにくい」という状態が続くと、
人はおのずとやわらかい食品を
好んで食べるようになります。
その結果、噛む筋肉がますます弱くなり、
やがて噛めなくなるという
お口の機能低下に至ってしまいます。
このように、はじめは
「噛みにくい」「飲み込みにくい」
だったものが、次第に
「噛めない」「飲み込めない」
という機能低下に至ってしまうのが、
オーラルフレイルの怖いところです。
さらに、オーラルフレイルは
お口の問題だけにとどまらず、
全身の衰え(身体的フレイル)にも影響します。
ある調査では、オーラルフレイルの人は
そうでない人と比べて、
要介護になるリスクが約2.4倍、
4年以内に亡くなるリスクが約2倍になると
報告されています。
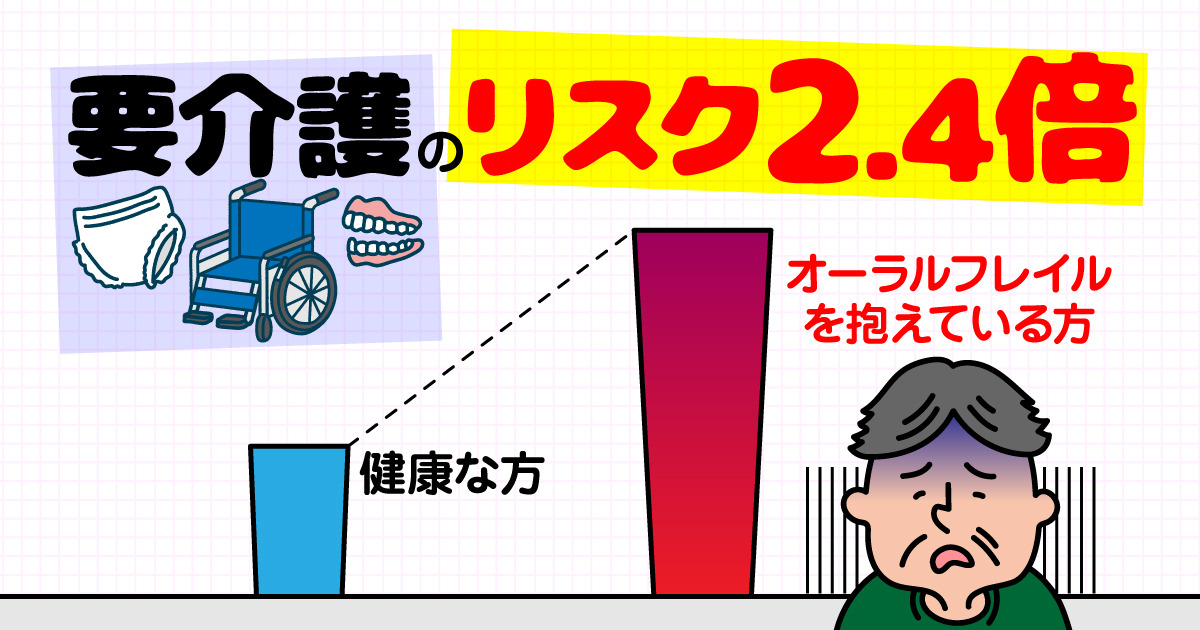
オーラルフレイルが原因で
要介護に至ってしまうと、
元の健康な状態に戻すのは難しくなります。
したがって、ほんの少しの衰えも
「年のせい」と軽く見ず、
早め早めに対処していくことが肝心です。
◆ささいな変化に気づくことから!
早期対応が大切です
食べこぼしや、むせやすくなるほか、
お口の渇きや
普段の会話で言葉をはっきり発音できないなど、
これらに身に覚えがある場合は、
オーラルフレイルが疑われます。

大切なのは、
オーラルフレイルを自覚したら
早期の機能改善に取り組むことです。
いつまでもおいしく食事を楽しみ、
健康的な生活を送るためにも、
早めに歯科医院で相談し、
適切な指導を受けましょう!
西歯科クリニック
〒619-0218
京都府木津川市城山台1-14-1
TEL:0774-73-6767
URL:https://nishi-dc.net/
Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm
口腔ケアが命を守る!歯周病と心臓病の密接な関係

こんにちは。院長の西です。
8月に入り、いよいよ夏本番となりました。
厳しい暑さが続きますが、
こまめな水分補給と体調管理を心がけ、
この夏を乗り切っていきましょう。
さて、8月10日は
「健康ハートの日」です。
810=ハートの語呂にちなみ、
心臓病の予防キャンペーンの一環として
日本心臓財団が提唱しました。
日本人の死亡原因第2位の心臓病は
歯科とも密接に関わっており、
口腔ケアが不十分だと
心筋梗塞などの重篤な病気に
かかりやすくなることが
わかっています。
そこで今回は、
あまり知られていないお口と心臓の意外な関係や
そのリスクについて、詳しく解説していきます。
◆歯周病になると
心臓病のリスクが2倍に!?
「歯周病」と聞くと、
お口だけの問題と感じるかもしれません。
しかし、近年は世界各国の研究によって、
歯周病が全身のさまざまな病気と
関係していることがわかってきました。
心臓病もそのひとつで、
国内で実施されたある調査では、
歯周病の疑いが強い人は、
そうでない人と比較して
心筋梗塞の発症数が約2倍に上るとの
データが報告されています。

これまで、心臓病の危険因子としては
高血圧や肥満、喫煙などが
主に挙げられていましたが、
ここにきて「歯周病」も
無視できない存在であることが
明らかになってきたのです。
◆歯周病が心臓に影響するのはなぜ?
歯周病と心臓病、
一見すると無関係に思える
この2つの病気に
いったいどのような関わりがあるのでしょうか。
そのメカニズムについては、
現在までに次の2つの説が
考えられています。
1つは、歯周病菌が血流に乗って心臓へ運ばれ、
血管に炎症を起こすという説です。
この炎症によって心臓の血管の壁が厚くなると、
いわゆる「動脈硬化」が進行し、
狭心症や心筋梗塞を引き起こします。
実際に、動脈硬化を起こした患者さんの
心臓の血管を調べた研究では、
数種類の歯周病菌が
発見されたという報告があります。

もう1つは、歯ぐきの炎症そのものが
心臓病をはじめとする
全身の病気の引き金になるという説です。
歯周病で歯ぐきが腫れると、
その部位からは炎症に関連した
さまざまな物質が放出されます。
これらの物質が心臓に運ばれると、
血管などに悪影響を及ぼすことがわかっています。
◆命を守るためにも歯を大切に!
生活習慣病の予防といえば、
「食事」「運動」「禁煙」「睡眠」などが
重要視されてきました。
これらに加えて
「口腔ケア」も徹底することが、
今後の生活習慣病予防における
大切な取り組みになります。

健康診断だけでなく、
歯科での定期検診も欠かさずに、
常に良好なお口の状態を目指しましょう!
西歯科クリニック
〒619-0218
京都府木津川市城山台1-14-1
TEL:0774-73-6767
URL:https://nishi-dc.net/
Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm
睡眠不足は歯にも悪い?知っておきたい眠りとお口の関係

こんにちは、院長の西です。
7月に入り、夏の暑さが
本格的になってきました。
昼だけでなく夜も暑さが続くと
寝苦しさを感じることで、
なかなか寝付けずに睡眠不足に陥ることも。
この睡眠不足は
心身の健康にとっての大敵ですが、
実はお口にも悪影響を及ぼすことを
ご存じでしょうか?
今回は睡眠とお口の健康の関係性について
お話ししていきます。
◆睡眠不足で歯が危険にさらされる!?
不十分な睡眠によるリスクのひとつが
むし歯の進行です。
「しっかりと歯みがきをしていれば大丈夫」
と思われるかもしれませんが、
これだけでは
むし歯を防げない恐れがあるのです。
では、どのようにして睡眠不足が
むし歯の進行を招くのでしょうか?
その要因は、だ液の減少です。
だ液はお口の中の汚れを洗浄したり、
歯の修復を促したりすることで、
むし歯の進行を防ぐ役割を果たしています。
しかし、睡眠不足によって
自律神経が乱れると、
だ液の分泌量が減少します。
この結果、だ液によって
歯を守る働きが不十分になり、
むし歯が進行しやすくなります。
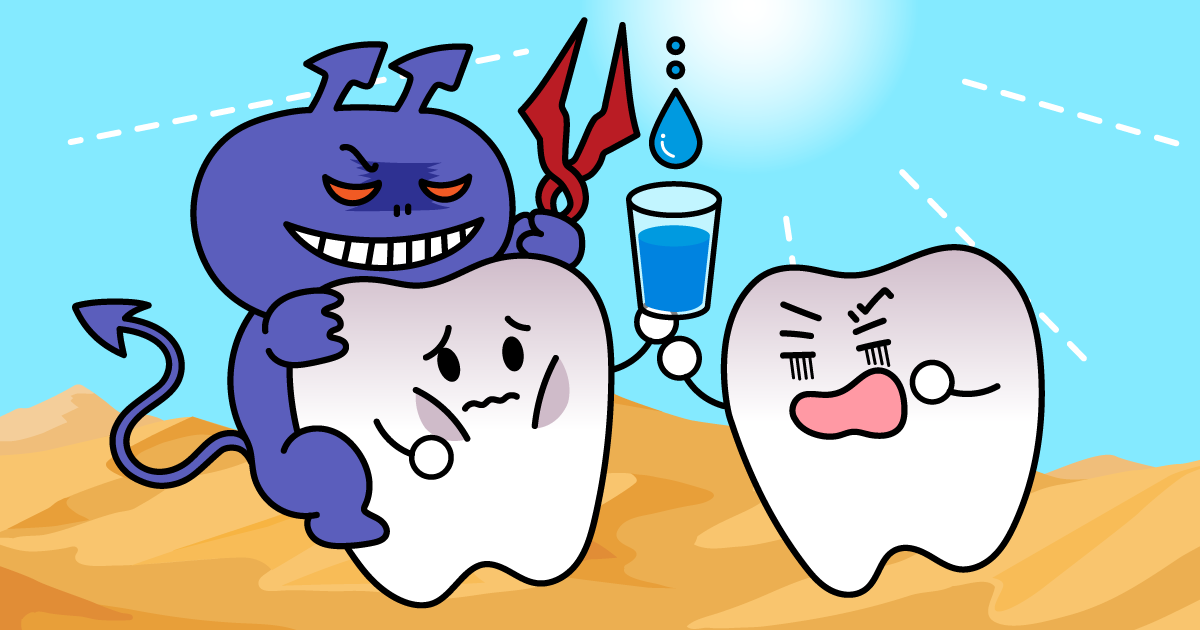
◆むし歯だけじゃない!?
睡眠不足によるもうひとつのリスク
睡眠不足によって引き起こされる
もうひとつのリスクが歯周病の悪化です。
歯周病は歯を支える骨が
溶けてしまう病気で、
最悪の場合は
歯が抜けてしまう恐れもあります。
では、睡眠不足と歯周病は
どのように関係しているのでしょうか?
これらを結びつける
キーワードが「糖尿病」です。
糖尿病は血液中の血糖の増加により、
やがてさまざまな合併症を引き起こす病気で、
数ある発症要因のひとつに
睡眠不足が挙げられています。
そして、糖尿病は
先に述べた歯周病と深い関係があり、
相互に症状を悪化させることが
明らかになっているのです。

いずれも自覚症状に乏しいため、
「気づいたら糖尿病も歯周病も悪化していた…」
といった事態にもなりうる、
まさに恐ろしい病気です。
◆良質な睡眠のカギは「歯の本数」にあり
先にご紹介したケースとは逆に、
歯の状態が睡眠時間に影響を及ぼすことも
あると言われています。
ある研究では、
歯の本数が少ないと睡眠時の呼吸を妨げ、
睡眠時間に影響する恐れがある、
との指摘をもとに、
調査が実施されました。
その結果、歯の本数が少ない人は
20本以上歯がある人に比べて、
睡眠不足、または長時間眠りすぎるリスクが
高くなることが明らかになりました。
このように、お口と睡眠は
お互いに深い関係性があり、
ときに健康そのものを左右するといっても
過言ではありません。
◆お口のケアと良好な睡眠で
健やかな毎日を!
健やかな生活を送るためには
良質な睡眠とお口の健康維持、
どちらも欠かすことができません。

毎日の生活習慣を整えつつ、
お口の状態に不安がある方は
早めに歯科を受診することをおすすめします。
日々のセルフケアで
万全の対策を心がけて、
暑い夏も元気に乗り切りましょう!
西歯科クリニック
〒619-0218
京都府木津川市城山台1-14-1
TEL:0774-73-6767
URL:https://nishi-dc.net/
Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm
気になる歯石、自分で取っても大丈夫?

こんにちは、院長の西です。
6月に入り雨模様が続くこの時期は、
なんとなく気分がすぐれない日も
あるかもしれません。
そんな気だるさから、
普段は当たり前に行っている習慣を
疎かにしてしまうと、
健康状態が悪化するリスクを
招くことがあります。
そのリスクのひとつが「歯石」です。
日々の歯みがきが不十分だと
歯に付着した歯垢(プラーク)が
やがて歯石となり、
色々な害を引き起こします。
中には
「歯石を自分で取り除いている」
という人もいるかもしれませんが、
この行為は効果が無く、
むしろ危険を伴うため注意が必要です!
◆毒性があるのは歯石ではなく、
歯石につく◯◯!
歯石とは、
歯の周囲に溜まった
細菌の塊である歯垢(プラーク)が
だ液に含まれるミネラル成分によって
石のように硬くなり、蓄積したものです。
歯石には大きく分けて、
目に見える黄白色の
「歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)」と、
歯ぐきの下に隠れている、黒っぽい
「歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)」があります。
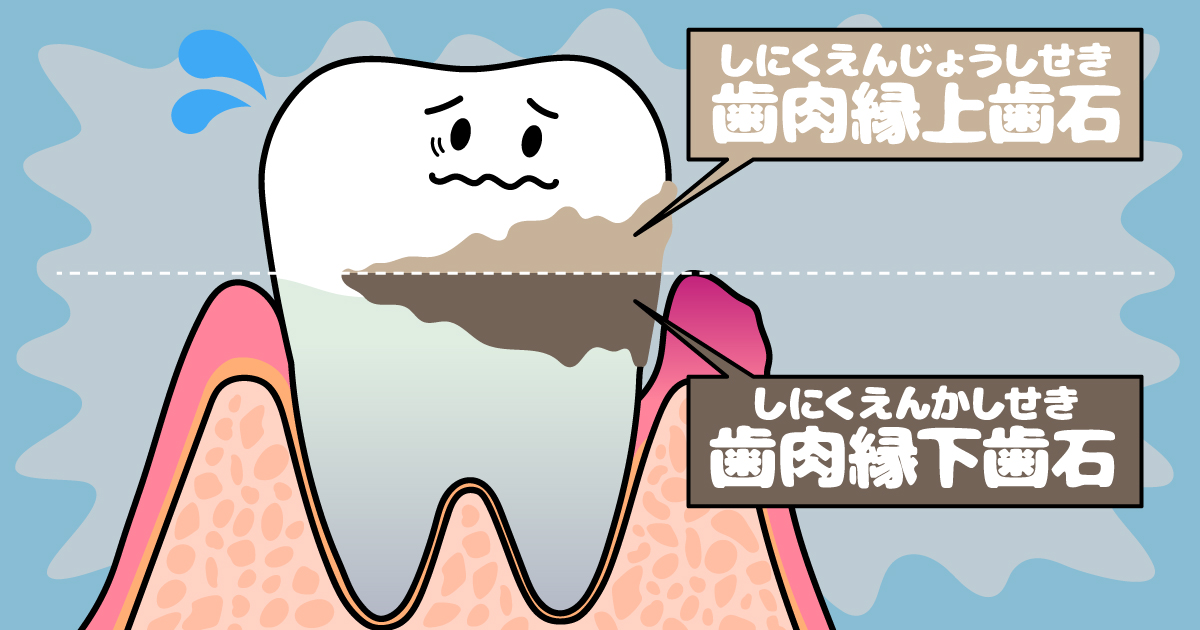
この歯石自体に毒性はありませんが、
お口の健康のためには
取り除くことが必須です。
その理由は、
ざらざらした歯石の表面が
細菌の繁殖にはうってつけの環境であり、
この細菌が、歯や歯ぐきに
悪影響を及ぼしてしまうからです。
◆歯石を放置するとこんなことが…!
細菌だらけの歯石を
除去しないまま放置すると、
やがて歯周病が悪化する
原因となります。
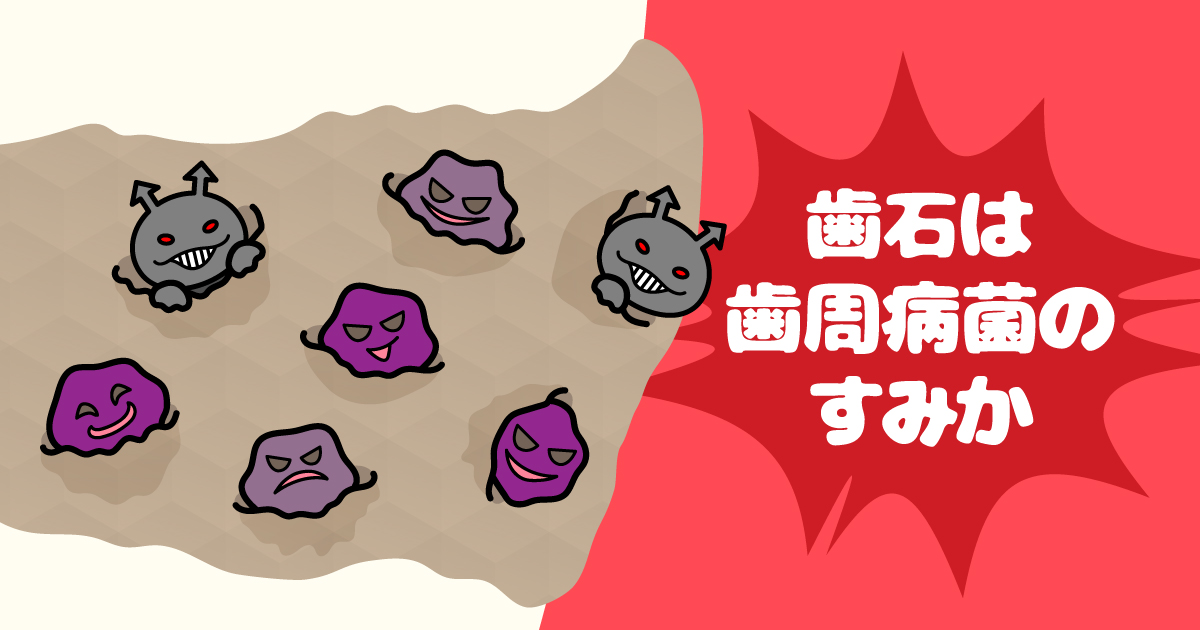
歯石の表面の凹凸に入り込んでいる細菌は、
通常の歯みがきでは完全に除去できません。
その結果、歯石がついた周囲の歯ぐきで
炎症が起こって腫れてしまい、
歯と歯ぐきの間のみぞ(歯周ポケット)が深くなります。
この環境下で歯周病菌が増えることで、
歯周病が悪化していきます。
さらに、歯周病菌は
悪臭を伴うガスを放つため、
口臭も強くなってしまいます。
これらを回避するためには、
細菌のすみかとなる歯石を
早めに取り除くことが肝心です。
◆絶対やめた方がいい…
自分で歯石を取る危険性とは?
歯石を早く取ったほうがいい、となると、
「自分で歯石を取ってしまおう!」
と考える人もいるかもしれません。
しかし、自分で歯石を取ろうとすると
歯や歯ぐきを傷つけることになり、
歯石を全て取ることも不可能です。
また、取り残された歯石に付着した細菌は、
変わらず毒素を出し続けるため、
歯周病や口臭が確実に悪化します。
このように逆効果にしかならないため、
自分で歯石を除去する
メリットはありません。

これらの理由から、
歯石を自分で取ることは絶対に避けましょう。
◆歯石の害、どうしたら食い止められる?
歯石への最善の対処法、
それはズバリ、
「定期的に歯科医院で取ってもらうこと」です。
歯石は一度取った後も、
お口の中のプラークが再び歯石となり、
繰り返し付着してしまいます。
そのため、一般的には
3~6か月に一度のペースで
定期的に歯石取りに通い、
きれいな状態を保つことをおすすめします。
お口の悩みのタネとなる歯石を
歯科医院で安全かつきれいに取り除き、
健康な歯ぐきを維持していきましょう!
西歯科クリニック
〒619-0218
京都府木津川市城山台1-14-1
TEL:0774-73-6767
URL:https://nishi-dc.net/
Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm
